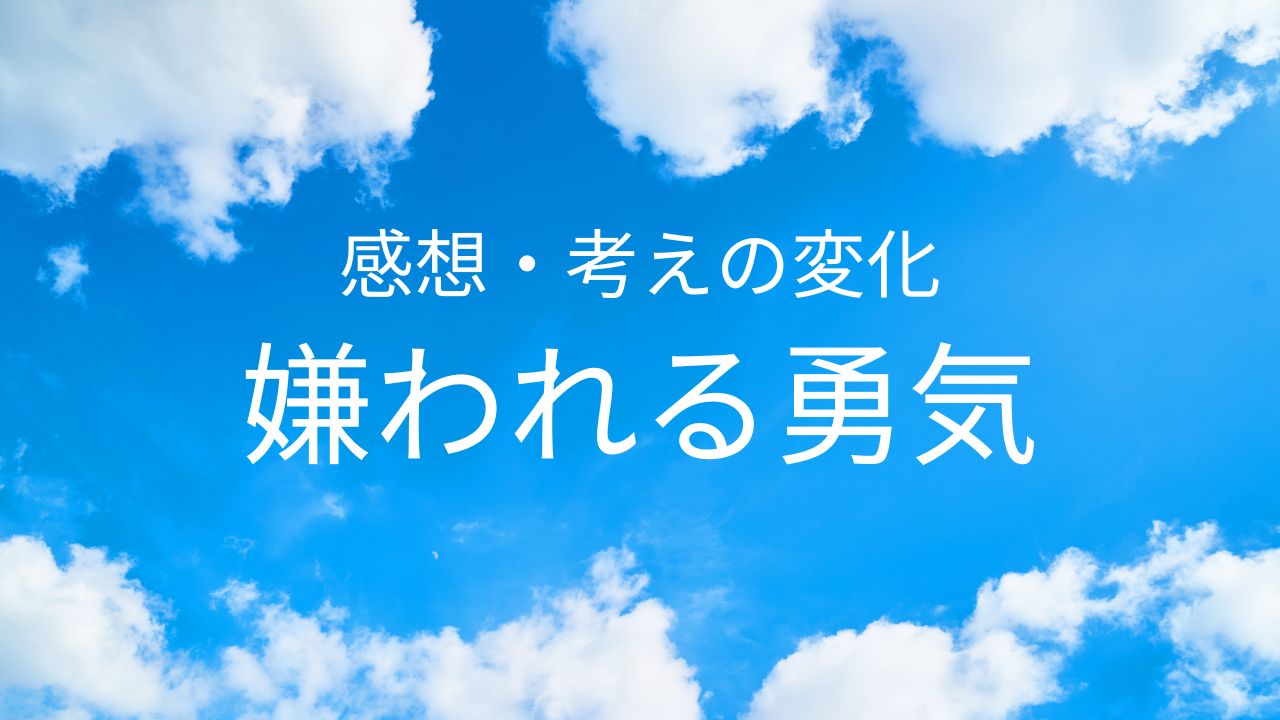Aさん
Aさん他人の目が気になって恥ずかしい。
もっと自信を持って行動したい。



他人なんか気にする必要ないですよ。
過去に他人が気になってばかりの私に勇気と希望を与えてくれたのが「嫌われる勇気」です。
この本を読んだことで、これまでと違う考え方ができるようになりました。
- 他人のことを気にせずに行動できるようになった
- あらゆる出来事をポジディブに捉えられるようになった
- 自分らしく振る舞えるようになった
他人の目を気にして辛いという方にはぜひ読んでほしい本です。これまでと違う考えを持つことができます。
読んでみた感想
衝撃的な内容ばかりで、理解できないことが多かったです。気になって何度も読み返すうちに理解できるようになりました。自分の狭い考え方を変えるのに十分な内容でした。
読む前は、「嫌われる勇気ってどんなものなんだろう?」と思っていました。できるなら誰からも嫌われずに、良い評価を受けていきたいのにわざわざ嫌われる必要ってあるのだろうかと考えてました。
ですが、本を読んだことで納得できました。嫌われることが自由への一歩ということです。
いくつか印象に残ったことについてまとめます。
- 承認欲求
- 自分と他者の課題
- 他者貢献
承認欲求
他者からの評価や承認欲求を求める生き方は、不自由であることを知りました。
良い行いをすることで、誰かに感謝されることはとても嬉しいことです。しかし、その行いを誰からも見てもらえてなかったり、感謝すらもされなかったら最悪な気分になります。
それなら
「人が見ているところでは良いことをして、見ていないところでは悪いことをしても構わない」という考え方になりかねないです。
本書には、承認欲求を求めて他者からの評価を気にすると他者の人生を生きることになり、不自由を強いられる人生になると書かれていました。
不自由を強いられてつまらない人生を送るなら、嫌われる覚悟を持って人生を送った方が楽しいと思いました。
自分と他者の課題
自分が言ったことに対して、相手がどう捉えるかは相手次第で自分がどうにかできるものではないと知りました。
本書では、親が子供に勉強を強いることについて、親が勉強するように怒っても勉強するかは子供が決めることと書かれてます。勉強しないという選択で最終的な結末を引き受けるのは子供であるから親がどうにかできることではないということです。
最終的な結末を受けるのは誰かを理解した上で、無理にやらせるのではなく、いつでも支援できるように見守ることが大事であるとわかりました。
自分が真面目に仕事をしても、上司がどのように評価するのかは上司の課題であってこちらが介入できるものでないと理解した上で、働く必要があると考えさせられました。
他者貢献
本書では「幸福とは貢献感」と書かれています。他者に貢献することで幸福を得られるのかどうか、半信半疑でしたが読んでみるとまさにその通りでした。
働いて「自分が誰かの役に立っている」ことを実感して、自らの存在価値を感じられる。「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、「わたし」の価値を実感するためにこそなされるもの。
自分の得意なことや真価を発揮して、誰かの役に立つことが自分の存在価値を表し、幸福になれると思いました。
本の簡単な紹介
「嫌われる勇気」は、アドラー心理学についてわかりやすく理解できる本です。
著者の「岸見一郎」氏と「古賀史健」氏が共著した本で、アドラー心理学の基本概念を通じて、他人の評価や期待からの解放、自己と向き合うためのヒントを教えてくれます。
本書は、「悩みの多い青年」と「アドラー心理学に精通した哲人」との対話形式で書かれています。
アドラー心理学について、読んでいて読者が引っ掛かる点を青年が代弁してくれるようになっており、理解がしやすくなっています。また、哲人もその点についてわかりやすく解説してくれます。
この本から学べる内容は下記です。
- 自己肯定感の重要性
- 自己成長と向き合う勇気
- 周囲との関係性の変容
自己肯定感の重要性
他人の評価に振り回されずに、自己肯定感を育てることの重要性を説いています。
本書では、人間関係の捉え方によって相手を敵とみるか仲間とみるか解説しており、どう捉えるかは自分のライフスタイル次第と述べています。
縦の人間関係を築けば相手を敵と捉えますし、横の人間関係であれば仲間と捉えられます。どう捉えるかは自分のコンプレックスやライフスタイル次第です。
承認欲求についても述べており、人に評価される人生を送るくらいなら他者から嫌われる勇気を持って自由に生きた方がいいと書かれています。
嫌われる覚悟を持つことで、他人の意見に左右されずに自分の信念を持ち、自分を受け入れることができると学びました。
自己成長と向き合う勇気
成長は快適な領域を離れ、新たな挑戦に立ち向かうことから生まれます。
本書では、人生が変わらないのを嘆いているのは自ら「変わらない」と決心しているからと述べており、この解決策が今のライフスタイルを「やめる」必要があることです。
やりたいことがあっても、それには成功と失敗する2つの可能性があります。もしそれをやらずに「もしも〇〇だったら」と考えることで可能性の中を生きることができます。
ですが、それでは「変わらない」と決心しているにすぎないと。今の自分を受け入れ、前に踏み出す勇気が必要と述べています。
自己成長の過程で失敗や評価の低さを受け入れ、それをチャンスと捉えて一歩ずつ前に踏み出していくことが重要なのだと学びました。
周囲との関係性の変容
他人との関係においても、嫌われる覚悟を持つことで、相手の評価や期待に囚われずに本当の自分と向き合い、より深いコミュニケーションやつながりを築くことができます。
本書では、対人関係のゴールが、課題の分離から共同体感覚と変化させることと書かれています。
課題の分離によって、相手に対して考えを強制することなくいつでも手助けできるようにしておく「勇気づけ」をすることが大事であること。
そして、ありのままの自分を受け入れ、他者を信頼して貢献することを繰り返すことで、共同体感覚にたどり着けるとわかりました。
自分を認め、相手を信頼して、相手に貢献することを繰り返すことで幸福を感じられるのだと学びました。
考えの変化
この本を読んだことで考え方に変化がありました。
- どんな出来事でも捉え方で変わる
- 課題の線引き
- 自分で変わろうとすること
どんな出来事も捉え方で変わる
これまで自分に起こった出来事をネガティブに捉えることが多くありました。
ですが、この本を読んだことでネガディブからポジティブに捉えることが多くなりなりました。ネガティブなことは自己成長のためにあること、失敗から学ぶことが人生の糧になりました。
人生を変えるためにネガティブなことをネガティブのままにするのをやめて、自分の成長につなげることに決心しました。
このおかげで、どんな出来事も自分のためにあるのだと捉えることができて、物事の見え方が変わりました。
課題の線引き
これまで自分の発言で相手がどう思ったのか、考えすぎることが多かったです。
本書の課題の分離から学び、読んだことで必要以上に相手のことを考えたり、介入しないようにしました。
言ってしまったことはしょうがないし、それを相手がどう捉えるのかは相手の課題であってこちらが介入できないものとして、考えないようになりました。また、それでお互いに不利益を被ろうとも仕方のないことだと割り切ることができて、仕事もしやすくなりました。
課題の分離ができるようになったことで、相手に支援ができるようになったり、内容の濃い人付き合いができるようになりました。
貢献すること
これまで自分本位で動くことが多かったです。
本書では、他者貢献することで幸福感が得られると学びました。
そのことに従って、自分が最大限に能力を発揮できて、他人へ与えられることは何かで考えた上で行動したところ幸福を感じられました。
そのことを体験してからは、家族に対してや仕事においても貢献することを意識して動くようにしています。
まとめ


「嫌われる勇気」は、他人からの評価にとらわれることなく、自己肯定感を育て、成長を果たすための方法についてアドラー心理学視点からヒントを与えてくれます。
この本を読むことで、自分自身を受け入れ、逆境や挑戦にも立ち向かう勇気を得る手助けとなることでしょう。また、他者との人間関係や仕事においても大いに今後の人生に役立ちます。
私自身もこれまでの自分を受け入れて、仕事や人間関係に向き合う上でかなり役立ちました。
自分自身と向き合い、自分の人生を切り拓くための一歩として、ぜひ一読をおすすめします。